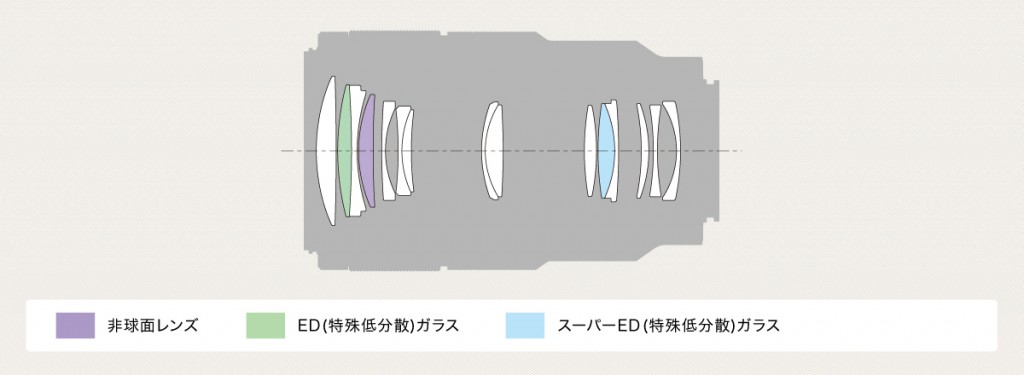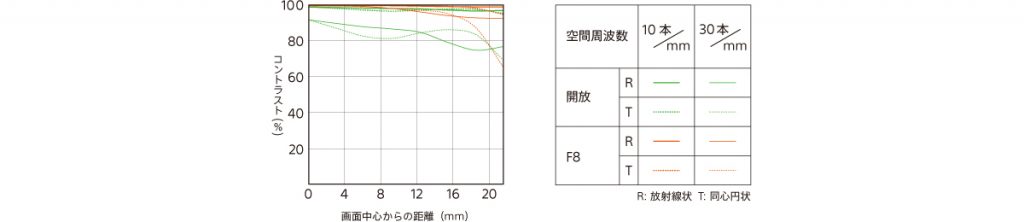レンズ
ソニー FE 90mm F2.8 Macro G OSS 最新情報まとめ
このページでは一眼カメラ用交換レンズ「FE 90mm F2.8 Macro G OSS」の情報を収集しています。
最新情報
データベース
購入早見表
フィルター購入早見表
レンズデータ
| レンズ仕様 |
| 名称 |
FE 90mm F2.8 Macro G OSS |
| 型名 |
SEL90M28G |
| レンズマウント |
ソニー Eマウント |
| 対応撮像画面サイズ |
●35mmフルサイズ |
| 焦点距離(mm) |
90 |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 |
135 |
| レンズ構成 (群-枚) |
11-15 |
| 画角 (APS-C) *1 |
17° |
| 画角 (35mm判) |
27° |
| 開放絞り (F値) |
2.8 |
| 最小絞り (F値) |
22 |
| 絞り羽根 (枚) |
9 |
| 円形絞り |
○ |
| 最短撮影距離 (m) |
0.28 |
| 最大撮影倍率 (倍) |
1.0 |
| フィルター径 (mm) |
62 |
| ADI調光対応 |
- |
| 手ブレ補正 |
レンズ内手ブレ補正方式 |
| 手ブレ補正段数 |
- |
| テレコンバーター (1.4x) |
- |
| テレコンバーター (2.0x) |
- |
| フードタイプ |
丸形バヨネット式 |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) |
79 x 130.5 |
| 質量 約 (g) |
602 |
更新情報
- 2018-06-21:The Digital Pictureがレビューを開始したようです。既に画質比較ツールに追加したみたいですね。
- 2017.11.21:レビューにPhillipreeeveを追加しました
- 2017.7.26:ページを全体的に改訂
- 2016.8.18:ページを全体的に改訂
-レンズ
-FE 90mm F2.8 Macro G OSS