このページではパナソニックのフルサイズミラーレス「LUMIX S5」に関する最新情報・噂を収集しています。
データベース
最新情報
- 新型グリップDMW-BG1に対応する LUMIX S5 用ファームウェアが公開 2023年10月18日
- 「LUMIX S5II」と「LUMIX S5」の外観やスペックの違い 2023年1月6日
- ウェブ上の断片的な情報はLUMIX S5 Mark IIの近日登場を示唆してるのか? 2022年12月24日
- LUMIX S5 Mark IIは現行モデルよりも位置づけと価格が高いS1のようなモデルとなる? 2022年11月9日
- パナソニックは2023年のCP+に向けてLUMIX S5 Mark IIを発表する? 2022年11月7日
- パナソニックがLUMIX6機種の最新ファームウェアを公開 2022年7月27日
- LUMIX Sシリーズ キャッシュバックキャンペーン 対象製品早見表【2022夏】 2022年7月22日
- LUMIX Sシリーズ キャッシュバックキャンペーン 対象製品早見表【2022春】 2022年2月24日
- パナソニック「LUMIX S」キャッシュバックキャンペーン【2021夏】 2021年7月18日
- パナソニックがSシリーズでBRAW出力に対応するファームウェア公開を予告 2021年6月23日
特集記事
レビュー
購入早見表
| LUMIX S5 ボディ | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
| ソフマップ |
|||
| ビックカメラ |
PREMOA |
||
| LUMIX S5 レンズキット | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
| ソフマップ |
|||
| ビックカメラ |
PREMOA |
||
関連カメラ
関連記事
- 新型グリップDMW-BG1に対応する LUMIX S5 用ファームウェアが公開
- 「LUMIX S5II」と「LUMIX S5」の外観やスペックの違い
- ウェブ上の断片的な情報はLUMIX S5 Mark IIの近日登場を示唆してるのか?
- LUMIX S5 Mark IIは現行モデルよりも位置づけと価格が高いS1のようなモデルとなる?
- パナソニックは2023年のCP+に向けてLUMIX S5 Mark IIを発表する?
- パナソニックがLUMIX6機種の最新ファームウェアを公開
- LUMIX Sシリーズ キャッシュバックキャンペーン 対象製品早見表【2022夏】
- LUMIX Sシリーズ キャッシュバックキャンペーン 対象製品早見表【2022春】
- パナソニック「LUMIX S」キャッシュバックキャンペーン【2021夏】
- パナソニックがSシリーズでBRAW出力に対応するファームウェア公開を予告
海外の評価
DPReview
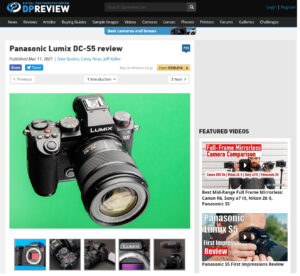
DPReview:Panasonic Lumix DC-S5 review
| 長所 | 頑丈でコンパクトな防塵防滴ボディ ボディ内手ぶれ補正 最高に優れたJPEGエンジン 応答性のあるAFと検出機能 大部分の状況で優れた追従性 優れた9600万画素ハイレゾモード フルサイズ4K 30p APS-C4K 60p アナモルフィック・4:2:2 10Bit 信じられない程柔軟な動画機能群 デュアルSDカードスロット USB充電 バッテリーライフ |
|---|---|
| 短所 | コントラスト検出方式のC-AF 一部動画は30分制限 平凡なファインダー解像度 連写速度が遅い 1スロットのみUHS-II対応 フルサイズHDMIが良かった 配置不良のAF-ONボタン |
パナソニックに興味はあったが、900gのLUMIX S1Rや、1kgで動画中心のLUMIX S1Hを持ち歩きたくなかった人に、LUMIX S5が最適だ。S1のように静止画と動画のハイブリッドでありながら、よりポータブルなカメラに仕上がっている。
とても頑丈な防塵防滴カメラであり、S1やS1Rと同じように堅牢なカメラだ。とはいえ、背面のコントロールはやや混雑しており、EVFの解像度は平凡で、HDMIポートはA端子ではなく壊れやすいD端子だ。そして、2つのSDカードスロットのうち、UHS-IIに対応しているのは1つだけだ。(S5で撮影するような動画はUHS-Iで十分だが)
S5は、起動時間、メニュー操作、フォーカシング時にとても優れた応答性を示した。さらに新設計のバッテリーはCIPA規格で440?470枚となり、実際の撮影ではほぼ間違いなくこの数値を上回る。ただし、連続撮影は、C-AFで5コマ/秒と低めだ。
パナソニックは、S5のAFシステムでいくつか改良が見られた。顔/瞳/頭/体の検出は反応が良く、正確だ。被写体の追従性は、クラス最高とまではいかないものの良好である。フォーカスアルゴリズムの調整により、C-AF使用時の「ゆらぎ」は軽減されているが、完全になくなったわけではない。
画質は素晴らしく、このクラスの最高カメラに匹敵するものだ。RAW画質は低ISO・高ISOともにディテール十分だが、他のカメラに比べてモアレがやや多いのは気になる。JPEG画質は、高感度時に美しい色と非常に優れたノイズリダクションだ。さらにS5は、このクラスのカメラでは唯一、マルチショットモードを搭載しており、カメラ内で9600万画素のRAWおよびJPEG出力に対応、効果的な動体補正を行うことができる。
動画では、10Bitの4K 30p(フル画角)、4K 60p(APS-Cクロップ)、FullHD 180fpsを撮影可能だ。さらに、ゼブラ、波形、ベクトルスコープ、V-Log/V-Gamut、RAW出力、垂直構図の撮影など、多彩な機能を搭載している。オーバーヒートを避けるため、一部の解像度では30分の録画制限がある。
総合的に見て、パナソニックLUMIX DC-S5は、動画にも強い関心を持つフォトグラファーにとって、デザイン性に優れた機能満載カメラとなる。最も大きな問題はオートフォーカスのフラッター・ウォブリングで、改善されたとはいえ動画に悪影響を及ぼす可能性がある(静止画を撮影する際には、単に気が散るだけ)。しかし、S5は我々の評価で「銀賞」を受賞するのに十分に見事なカメラである。
Z 6IIと比べて
ニコンZ 6IIは、ほぼ同様の機能を備えているが、S5のような揺らぎが無い優れたオートフォーカスシステムを実装し、美しい電子ビューファインダー、より高速な連続撮影などの点で、さらに高い評価を得ている。画質や動画もS5と同様だ。同じセンサーを使用していると考えられるため、驚くことではない。S5は10Bitの4:2:2に対応している(Z 6IIは10BitのLogをHDMIで出力可能)、波形やベクトルスコープの表示機能を備えているため、動画部門ではS5に軍配が上がる。難しい比較となるが、最終的に「静止画と動画のどちらをメインに撮影するか」ということがポイントとなるだろう。
EOS R6と比べて
キヤノンEOS R6は、S5とはまったく異なるセンサー設計(正確には2000万画素のデュアルピクセルCMOS)を採用しており、その違いはZ 6 IIと同様だ。R6はキヤノンの考え抜かれたエルゴノミクス、より高解像度のビューファインダー、高速連続撮影、見事なボディ内手ぶれ補正を搭載している。デュアルピクセルAFシステムは、静止画と動画の両方でとても良好に機能する。R6は、波形モニタやベクトルスコープに対応していないものの、小さなクロップで4K 60pの映像を撮影することができ、10Bitの内部記録にも対応している。ただしローリングシャッターは、このクラスの他のカメラよりも目立つ。画質と動画がしっかりとしたカメラだ。
α7 IIIと比べて
ソニーα7 IIIはS5よりも数年古いカメラだが、画質や驚異的なバッテリーライフ、幅広いレンズの選択肢は検討に値する。高性能ではあるが、AFシステムはソニーの最新のものではない。S5はエルゴノミクスに基づいたデザイン、液晶の解像度やタッチパネルの操作性、動画機能、そしてビルドクオリティの面で勝っている。ソニーα7Cはよりコンパクトで、AFシステムも改善されているが、他のカメラにはあるいくつかのコントロールが無い。
ePHOTOzine

ePHOTOzine:Panasonic Lumix S5 Review
- ボディは金属製でしっかりとした質感だ。フロント・リアのコマンドダイヤルは適切に、期待通りの配置である。
- モードダイヤルやドライブダイヤルは金属製だ。
- 優れた耐候性を備えており、天候を心配する必要が無い。
- 大きなグリップとサムレストでカメラをしっかりと握ることが出来る。
- シャッターボタンの背後にはWB・ISO・露出補正を素早く変更できるボタンがある。さらに背後にはスタイリッシュな録画ボタンを搭載。
- 電源オン・オフのスイッチはモードダイヤル同軸だ。
- モードダイヤルはP/A/S/Mに加え、インテリジェントオート・動画・S&Qと3つのカスタム枠を持つ。
- ドライブダイヤルはシングルショットに加え、連写や6K/4KPHOTO、インターバルタイマー、セルフタイマーに対応している。
- AFジョイスティックは富士フイルムほど小さくないが、比較的小さなサイズである。
- コントラスト検出方式のオートフォーカスを備えている。大部分の状況で非常に高速だが、動画撮影ではピントが前後にちらつく可能性がある。静止画では様々なオプションが存在し、低照度では-6EVまでのフォーカスが可能だ。
- ファインダーは236万ドットのOLEDパネルを使用し、0.74倍となる光学系を備えている。色再現性は良好でアイポイントが長く使いやすい。
- バリアングルモニタは動画撮影や自撮りに最適だが、ケーブルポート利用中はモニタと干渉する可能性がある。モニタの解像度は良好で視野角も広い。
- メニューはきちんと配置され、静止画・動画で個々のセクションがある。モードダイヤルで静止画・動画を切り替えることで、メニューが自動的に調整され、素早く設定項目へアクセスが可能となる。
- バッテリーはCIPA規格で440/470枚の撮影が可能だ。省電力モードでは1500枚まで増加する。バッテリーグリップを追加して900枚まで拡張することが可能だ。
- デュアルSDカードスロットは片方のみUHS-IIに対応している。
- 実写では素晴らしいイメージを出力可能だが、高感度ISOで撮影した場合はRAW現像のほうが良好な結果となる場合がある。
- ポートレートの撮影では9%ほどのカットで瞳にピントが合っていなかった。
- 色再現性は良好だ。様々な仕上がり設定を選ぶことができ、コントラストやハイライト、シャドウ、彩度、シャープネス、ノイズリダクションを個別に設定可能だ。
- 露出は信頼でき、露出補正を使う必要性を感じることは滅多になかった。
- ハイレゾモードは三脚を使う必要があるものの、カメラ出力で9600万画素のイメージを生成可能だ。
- ISO50はダイナミックレンジが狭くなるものの、非常に低ノイズだ。
- ISO100からISO1600までは低ノイズで良好なディテールを維持している。
- ISO3200でディテールが僅かに低下し、ISO6400でさらに少し低下する。
- ISO12800ではノイズが増加してディテールが大きく低下する。
- ISO25600ではノイズが強くなりディテールが失われる。
- ISO51200でさらにディテールは低下するが、彩度は維持している。それ以上の感度は避けたほうが良いだろう。
- AWBとAWBcの違いはとても小さい。
- 動画はAPS-Cクロップで4K 60p 10Bitを利用可能だ。フル画角では4K 30p 10Bitに対応している。8Bit動画の場合は無制限だが、10Bitの場合は連続撮影時間が30分に制限される。Full HDは180fpsまで利用できる。
- ファームウェアアップデートでDCI 4KやRAW動画が実装される予定だ。
- 動画撮影中の顔・瞳検出AFは良好に機能するが、瞳検出が外れると露出はフレーム全体を優先するようになる。
ビデオグラファーに訴求できる強みを持ち、同価格帯の競合カメラよりも優れたスペックと機能性を備えた魅力的な選択肢だ。さらに動画機能は強化される予定である。
静止画では優れたフォーカス性能と色再現性、ノイズ耐性を得ることができる。大多数のフォトグラファーが満足する十分な撮影機能や設定、モードを備えている。カメラは使いやすく、最も重要な設定に素早くアクセス可能だ。ただし、スポーツ写真の場合は7コマ秒の連写速度に注意する必要がある。
キットレンズの「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6」もたいへん素晴らしい。Lマウントシステムに投資する大きな理由となるかもしれない。レンズライナップが気になる場合はソニーEマウントと見比べながら検討すると良いだろう。
長所:S1と比べて小型軽量・優れた操作性・9600万画素ハイレゾモード・ボディ内手ぶれ補正・4K 60p
短所:4K 60pはクロップモードのみ・動画撮影時のフォーカス
PhotographyBlog

PhotographyBlog:Panasonic S5?Review
- パナソニックがリリースしてきたフルサイズミラーレスの中では最小・最軽量のカメラだ。そしてフォトグラファー・ビデオグラファーどちらにもアピールする機能を備えた、より低価格のオールラウンドカメラに仕上がっている。
- サイズは132.6×97.1×81.9mm、重量は630gと、従来のLUMIX S1と比べて遥かにコンパクトだ。定評のあるマイクロフォーサーズカメラLUMIX GH5と比べてもさらに小型軽量だ。
- 競合他社はS5よりよりも少し重いか同等だ。
- LUMIX Sシリーズに興味はあったが、S1ボディのサイズが気に入らなかった場合、S5は間違いなく気に入るはずだ。
- 小型軽量ボディだが、操作性を犠牲にしていない。実際、S1と見比べてみると、非常によく似ている。どちらも一眼レフスタイルのファインダーを搭載し、大きなグリップ、論理的に配置されたコントロールを備えている。
- 低価格ながら戦車のような堅牢性・防塵防滴仕様は健在だ。さらにS1と同じイメージセンサーや手ぶれ補正を搭載しており、この点で市場最高のミドルレンジカメラと言えるだろう。
- キットレンズとなる「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6」は汎用性があり、小型軽量で扱いやすい。S5との組み合わせはバランス良好だ。まるで同時に開発していたかのようである。キットレンズとして手に入れると実質200ポンドとなるのでお買い得だ。
- しっかりとグリップを握ることで片手での操作も可能だ。
- コマンドダイヤルの応答性は良好だ。シャッターボタン後ろのWB・ISO感度・露出補正ボタンは使いやすく、良く考えられている。
- 内蔵ポップアップフラッシュが無い。
- モードダイヤルと隣接した電源スイッチは非常に使い辛い。ただし、誤操作の可能性はほぼ無いだろう。起動速度は電源レバーからシャッターボタンへ指を置き換える速度と同じだ。
- この価格帯のカメラとしては唯一4K 60p 4:2:0 10Bit・4K 30p 4:2:2 10Bit内部記録を備え、アナモルフィック動画にも対応している。
- 特定の動画モードではフル画角では無くSuper35mmクロップを使用する。これは欠点となるが、それでもこの価格帯のカメラとしては素晴らしい機能性だ。HDMI出力時には4K 60p 4:2:2 10Bitも利用できる。
- 一部の画質モードでは連続撮影時間が30分に制限される。
- V-Logが初期装備されている。これは「L版」で無ければ「有償アップデート」でも無い。
- デュアルネイティブISO機能を搭載しており、ISO感度により回路を切り替えることが可能だ。ただし、S1Hと異なり手動で回路を切り替えることは出来ない。
- ALL-Iコーデックには対応しておらず、LongGOPのみだ。またフルサイズHDMI端子では無く、Micro HDMI端子を使う点に注意が必要である。
- 2020年末、さらに動画機能が強化される予定だ。
・DCI 4K
・5.9K RAW
・3.5Kアナモルフィック
・ベクトルスコープ
・シャッター角
・L.monochrome S
・L.Classic Neo - デュアルカードスロットだが、UHS-II対応は片方のみだ。
- LUMIX S1のような3Wayチルトでは無く、バリアングルモニタを使用する。この方式は自撮りや様々な角度での撮影に対応している。
- 電子ファインダーはLUMIX S1ほど高解像では無いが、見通しの良いファインダーだ。
- 改善された検出機能は顔や瞳が2倍、人体や動物の検出が5倍の速度になったとパナソニックが主張している。静止画・動画どちらも優れたAF-Sだと感じるが、AF-Cでは少し見劣りする。
- 間違いなくS1シリーズより高速で被写体をロックし、より確実にピントを合わせる。しかし、DFDコントラストAFらしいウォブリングは依然として明らかである。この点でソニーやキヤノンのAF方式に後れを取っている。
- 画質はISO50からISO6400までノイズレスだ。ISO12800から目立つノイズが発生し、ISO25600やISO51200でかなりのノイズが現れる。それでも実用的な画質だ。可能であればISO102400やISO204800は避けた方が良い。
- ハイレゾモードでJPEG出力だと最大で9600万画素だ。
特に安いカメラでは無いが、静止画・動画のハイブリッドユーザーにとって多くの点で魅力的なカメラだ。GH5より小型軽量ながら、遥かに高価なS1Hの主要な機能をほとんど搭載している。
小型軽量で、より優れた動画システム、バリアングルモニタ、信頼性の高いAF、優れたキットレンズなどを考慮するとLUMIX S1よりも魅力的だ。
5コマ秒と遅い連写速度、やや古く低解像なEVF、マイクロHDMIポート、コントラスト検出ベースのAFには注意が必要だ。間違いなく以前のDFD AFよりも優れているが、像面位相差AFを凌駕するほどでは無い。
全体的に見ると、ミッドレンジのフルサイズミラーレスとしては魅力的なカメラだ。強くおススメできる。
Xitek

- LUMIX S5はLUMIX S1シリーズの静止画・動画機能をGH5に似た携帯性の高いボディに凝縮している。S5をS1の簡易版と理解するのは正しく無く、より高度な内部記録に対応している。
- コアとなるセンサー・プロセッサーに違いは見られず、連写性能やバッファ、ファインダー仕様、モニタ解像度、手ぶれ補正などはS1が優れている。その一方、S5はバリアングルモニタを採用し、本体は小型軽量化され、動画機能が強化されている。
- ボディサイズはLUMIX S1/S1Rより遥かにコンパクトとなり、マイクロフォーサーズのGH5と同等、そしてキヤノンやニコンのミラーレスシステムと同サイズだ。
- ボディがマグネシウム合金で構成された防塵防滴仕様だ。放熱に最適なレイアウトで効果的に熱が外部へ伝導され、安定した長時間動画撮影が可能となっている。
- LUMIX S1と比べ、前面のFnボタン一つやFnレバーが無くなっている。
- 最大の変更点はカメラ上部だ。全体的なレイアウトはLUMIX G99と同じだ。S1の左肩に搭載していたダブルダイヤルが分割され、左にドライブダイヤル、右にモードダイヤルを搭載している。S5のモードダイヤルにはロックボタンが存在しない。
- LUMIX G99と同じく、モードダイヤル同軸の電源スイッチを搭載している。シャッターボタン周囲はコマンドダイヤルだ。
- 動画機能を重視しており、RECボタンをより押しやすくなっている。
- LUMIX S1と比べてファインダーの仕様は大幅に低下している。解像度は236万ドット、倍率は0.74倍だ。フルサイズミラーレスの中では比較的低スペックのファインダーである。ファインダー中心の撮影ではユーザーエクスペリエンスが大きく異なる。
- ボタンレイアウトにもいくつか変更が見られる。「LVF」ボタンがカメラ左背面へ移動し、操作ロックレバーが無くなっている。AFモードボタン・モードレバー・AFONボタン・ジョイスティック・Qボタン・ダイヤル・SETボタンなどは、ジョイスティックの長さが少し短くなっていることを除き、全て同様だ。
- S1のような3Wayチルトモニタでは無いが、GH5と同じバリアングルモニタを搭載している。モニタ解像度は184万ドットでS1より僅かに低解像だ。バリアングルモニタは左側面のケーブルと干渉しやすいので注意したい。
- 左側面にはマイク・ヘッドホン・HDMI・UCB-S 3.1を利用できるポートが備わっている。HDMIはフルサイズではなく、Dタイプの端子を使用するので気を付けよう。
- バッテリーは新型DMW-BLK22を使用する。このバッテリーの容量は2200mAhで、最新世代のキヤノン・ニコンと同等だ。S1と互換性は無いが、G9やGH5でも利用することが出来る。ただし、古いDMW-BLF19をLUMIX S5で使うことは出来ない。
- S1のようにXQD+SDスロットでは無く、デュアルSDカードスロットだ。UHS-II対応がスロット1のみであるのは残念だ。
- メニューインターフェースはS1シリーズとほぼ同じだ。
- シャッター方式はメカ・電子先幕・電子シャッター・自動切換え・電子シャッター+長秒NRなどいくつかの選択肢がある。
- 最新AFアルゴリズムを投資し、人間の頭部を検出することが出来るようになった。AFCも強化され、動きの速い被写体も追従できる。
- ボディ内手ぶれ補正は5段分の補正効果があり、レンズ側と組み合わせることで最大6.5段分の補正に対応している。手ぶれ補正をオンにすることで歩行中の動画撮影で振動が軽減しているのが分かる。
- S1と同じくハイレゾモードに対応しており、8枚の撮影から9600万画素の高解像写真を生成することが可能だ。2400万画素時より高精細な写真となるが、動く被写体が混じると不自然な描写となってしまう。
S5には新しく4800万画素モードも搭載している。 - イメージセンサーはLUMIX S1と同じ2420万画素CMOSセンサーだ。ISO100-51200に対応している。ISO800まではノイズレスだ。ISO1600からノイズが出始め、3200、6400で徐々に増加する。JPEGでは少し滲むものの綺麗な画質を維持している。
ISO12800-25600になるとノイズが増大し、ノイズ低減の効き目によってはディテールの損失が大きくなる。
ISO102400?204800ではカラーノイズが濃くなり、JPEGでも色被りが発生する。 - ダイナミックレンジは-1?-2のシャドウ復元は完璧だ。-3段分の復元ではシャドウに僅かなノイズが発生する。それでも概ね良好だ。基本的にS1と同じである。
- 動画は最大で4K 60p 4:2:0 10Bit・4K 30p 4:2:2 10Bitの内部記録に対応している。また、4K 60p 4:2:2 10Bitの外部出力も可能だ。150Mbpsを超える動画仕様の場合は30分の録画制限が発生する。
- V-Log・V-Gamutに対応しているほか、波形モニタやビューアシストも利用可能だ。さらにアナモルフィックモードや4K 60pタイムラプス、4K HDRなどに対応している。
- スローモーション撮影時は4KやFull HDでAFを利用可能だ。ただし、フレームレートが150fpsを超える場合はMF限定となる。
- デュアルネイティブISOを搭載しており、高感度ISO使用時に最適な回路に切り替わる仕組みを利用できる。
・通常:100/640
・V-log:640/1000
・HLG:640/4000
・Cinelike:200/1250
S1Hのように回路を手動で切り替えることは出来ない。 - 出力形式はMOVとMP4のみでAVCHDには対応していない。
- ファームウェアアップデートでHDMI出力時のRAW動画に対応し、ベクトルスコープなど様々な補助機能が利用可能となる予定だ。
以上のことからLUMIX S5は新しいポジションのフルサイズミラーレスであることが分かる。ファインダーやモニター、手ぶれ補正などの仕様がS1と多少異なるものの、動画機能が強化され、小型軽量で使いやすいデュアルSDカード仕様だ。売り出し価格は高いものの、キャンペーンでシグマ45mm F2.8 DG DNセットなどを購入することで実質的なボディ価格は大幅に改善される。コストパフォーマンスが高く、Lマウントで最も競争力のある製品となるだろう。
長所:S1と同じ静止画画質・5軸ボディ内手ぶれ補正・バリアングルモニタ・多彩な内部記録・改善したAFアルゴリズム・S&Qモード・USB充電と給電に対応・デュアルSDカードスロット。デュアルネイティブISO・小型軽量・150Mbps以下の動画撮影では制限なし・将来的に5.9K RAW動画対応
短所:連写速度が遅い・4K 60pで大きなクロップ・USB PD非対応・古いバッテリー使用不可・スロット1のみUHS-II対応
Digital Camera World
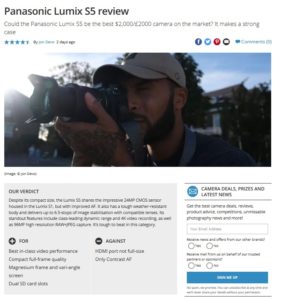
Digital Camera World:Panasonic LUMIX S5 review
Mobile01

Mobile01:Panasonic LUMIX S5 雙原生ISO加持 P家小型全幅機來臨
- パナソニックは像面位相差AFの対応に消極的であり、全てのカメラでコントラストAFシステムを採用している。
実績のあるマイクロフォーサーズシステムでは、フォーカス速度のレスポンスが他社と比べて全く見劣りしていなかったので問題無いだろう。 - 「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6」との組み合わせでフォーカス速度は非常に高速だ。HDMI出力を使用するとフォーカス機能に影響を与える事を発見しており、今回はHDMI出力を使わずに実写動画を用意した。
- 「LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.」と組み合わせて顔検出AFをテストした。意図的に途中で振り返りも混ぜてみたが、カメラへの影響は少ないようだ。被写体がカメラに近づくとピンボケの画像が多くなった。
- 逆光時のAF-Cは決して完璧とは言えず、フレームの大部分を被写体が占めている場合でも、ピントが背景に抜けてしまう場面があった。
- シャッターを切らずにオートフォーカスだけ動作する場合は被写体にピントを合わせ続けることが出来る。これは何を意味するのだろうか?
- オートフォーカス中はピントが合っているだけに悩ましい挙動だ。
- ハイレゾモードでは9600万画素の高解像データを出力可能だ。ハイレゾモードを使用することでディテールの再現性が大きく向上する。ただし、レンズやセンサーノイズなどの影響を受けるので9600万画素分の恩恵を受ける訳では無い。
- このカメラはデュアルネイティブISOに対応している。これは従来動画カメラVaricamシリーズでのみ利用可能だったものだ。
LUMIX S5はISO640とISO4000で回路が切替わる。ただし、S1Hと異なり手動で回路を切り替えることは出来ない。 - 僅かなノイズに気が付いたのはISO51200だ。ISO12800でもまだ綺麗な印象を受ける。
- ISO3200からISO4000へシフトした際に突然画質が良くなった。ISO3200は低ゲイン回路時に最も高いISO感度であり、回路が切替わった後のISO6400はISO3200よりもノイズが少ない。
- 手ぶれ補正はレンズ側とボディ側の両方を使って補正するDual.I.S 2に対応している。
- ミドルレンジのミラーレスだが、4K 60p動画に対応している。4:2:0 10 bitの4K 60p、または4:2:2 10Bitの4K 30pを利用可能だ。最高のビットレートは200Mbpsである。
- 4:2:2 10Bit 4K 60pはHDMI出力時のみ対応している。S1Hも4:2:2 10Bit 4K 60pの内部記録には対応していない。
- 4K 60p時は自動的にAPS-Cクロップへ移行するため、画角が大幅に狭くなる。
オートフォーカスは進化したと言われているが、個人的にはまだ不十分だと思っている。顔・瞳検出がオンになっている場合、被写体がゆっくり歩いても十分な成功率を得ることが出来ない。
正直なところ、ミドルレンジのLUMIX S5にデュアルネイティブISOは必要ないのではないかと考えている。LUMIXにこの機能が備わっているのはGH5SやS1Hなど最高クラスの動画向けモデルのみである。
肌の色調は好みがあるのであまり言及したくないが、パナソニックの肌色は本当に良好だ。他のカメラと比較してもLUMIX Sシリーズの表現は少し優れているように見える。
LUMIX S5の登場でS1のポジションが危うい。S5は下位モデルながらデュアルネイティブISOを搭載しており、スペック的にS1が優れている点は連写速度とフラッシュ同調速度、ファインダー仕様くらいだろう。
選ぶならもちろんS5だ。小型軽量でデュアルネイティブISOを使うことができ、高価なXQDカードを使う必要が無い。そしてバリアングルモニタを搭載している。LUMIX S1を選ぶ理由が思いつかない。
プロフェッショナルモデルを検討する場合はS1HやS1Rを検討すると良いだろう。
長所:小型軽量・バリアングルモニタ・4K 60p・V-log初期装備・6段分の5軸手ぶれ補正対応・使いやすいRECボタン・デュアルネイティブISO
短所:顔検出の追従性能・再生ボタンのレスポンス・HDMI出力時のAF性能・顔検出のAFに信頼性が足りない・Sレンズ群がまだまだ少ない
注意点:4K 60pはAPS-Cクロップ・S&QモードはMF・65:24や2:1のアスペクト比でオートエリアAFは使用不可・AF-Cでの連写撮影は速度が低下する
DPReview

DPReview:Coming into focus: how Panasonic's DFD gamble may yet pay off
- パナソニックがLUMIX S5で導入したオートフォーカスの変更点は印象的だ。最新版ですべての癖が解消されたわけでは無いが、特に静止画のAFCはかなり改善されているように感じる。
- しかしそれ以上に、これらの改善がどのように実現されたのか教えてもらった詳細が興味深い。これは、同社のDepth-from-focusシステムの利点と課題の両方を浮き彫りにするのに役立つ。
- このシステムは、一部で評判の悪いシステムだが、ここ数年で大幅に改善され続けている。S5は、DFDがどれだけ進歩したかを示すと同時に、まだ何が必要かを示唆している。
DFDとは
- 基本的には、フォーカスは距離の問題だ。特定の距離にある被写体からの光線がセンサー面に収束するまでレンズ光学系を調整することを指す。
- カメラがオートフォーカスを行う際に使用するアプローチには、大きく分けて2つある
ーピントが合っているポイントを見つけるまでハンチングするAF方式
ーシーンの奥行きを把握して、ハンチングせずにピントを合わせるAF方式 - DFDはパナソニックが開発した奥行きを解釈するためのシステムだ。わずかなピント調整を行い、その結果として画像がどのように変化したかを解析することで動作する。使用しているレンズのボケ特性を把握することで、その変化を判断し、シーンの深度マップを作成することが出来る。
- この課題は、シーン内の要素が動いている場合、カメラの深度マップを常に更新する必要があり、距離が変化しているため、より困難になる。
- そこで、被写体認識と被写体の動きを予測するアルゴリズムが活躍する。 カメラはシーンのどの深度で動きがあるのか、次に何が起こるのかを理解できるようにするからだ。
LUMIX S5で新しくなったこと
- パナソニックは、S5のオートフォーカスはいくつかの根本的な変更によって改善されたと述べている。その一部は、被写体認識の改善だ。
この機能はディープラーニングに基づいており、カメラが何に焦点を合わせればいいのか、そして何から離れてリフォーカスしてはいけないのかを知るのに役立つものだ。 - 例えば、目をそらしているときに人間の頭を認識するアルゴリズムを教えることで、カメラは認識していた顔が突然「消えた」ときに、新しい被写体を見つけたり、フォーカスを変えたりする必要がないことを理解する。
- もう一つは、利用可能な処理能力をより有効に活用するため、AFコードを書き換えたことだ。
S5の開発中、パナソニックのエンジニアは被写体認識と追従動作の両方で機械学習アルゴリズムに頼る必要がないことを発見した。機械学習による認識と、既存の高速な距離と動きのアルゴリズムを組み合わせることで、処理能力が解放され、プロセスをより頻繁に実行できるようになった。 - また、ソフトウェアの改良により、AFシステム全体の動作が高速化され、より多くの情報をプロセッサに提供できるようになった。
- これらの変更の結果、少なくとも静止画撮影者にとってオートフォーカスが大幅に改善し、コントラスト検出AFのハンチング依存度が少なくなっている。
- これにより、ファインダー内におけるフォーカスの乱れが減り、被写体を追従しやすくなった。フォーカス精度が向上するだけでなく、より良い体験が得られる。
動画
- しかし、このアプローチは主に静止画撮影の利点だ。撮影中の動画と同じような方法でセンサーを読み出さなければならないため、動画では処理速度の向上が難しい。
- 静止画モードでは、センサーフィードの解像度(空間解像度またはビット深度)を下げることで読み出し率を上げ、AFシステムが新情報を得る頻度を高めることができる。
そして、フォーカス中の低解像度フィードは、出力画質に影響を与えない。 - 高解像度動画モードでは、ビット深度、ピクセル解像度、フレームレートでセンサーを動作させる必要がある。せいぜい、出力フレームレートの2倍でセンサーを読み取ることができるだけだ。
- 動画は通常、フレームレートの2倍のシャッタースピードを使用して撮影している。
- 問題は、フルサイズセンサーが大きく、読み出すのが遅いということだ。S5のセンサーは、通常12ビットモードで読み出すため、21ms以上かかるソニーa7 IIIのようなものと非常に似ている。
24pの動画で48fps駆動を実行するのに十分な読み出し速度ではない。 - この課題があるにもかかわらず、パナソニックはこの最弱モードでもAFレスポンスを再調整し、不要なリフォーカスが起こりにくいようにしている。
輝かしい明日
- S5のアップデートは、いくつかのことを示している。第一に、パナソニックはカメラに対する批判を十分に認識しており、現在のハードウェアからできる限りのことを絞り出すために、ソフトウェアの微調整を続けている。
- しかしそれ以上に重要なことは、静止画撮影時、特に静止画の連写撮影時にAFCを使用した場合の改善点を見ると、これまでの欠点は必ずしもDFDのコンセプトに内在する欠点ではないことが分かった。
- センサー読み出し速度と処理能力向上によって改善できる側面だ。改善結果は見れば分かる。
- 長い目で見れば、ハードウェアが高速化するにつれて良くなるAF方式にコミットし続けることは、イメージセンサーに位相差センサーを埋め込むアプローチよりも良い選択であることが証明されるかもしれない。
- しかし、特に動画の分野でDFDはまだまだ改善の必要性が高い。フルサイズ購買層が他社のシステムを導入する前に、高速読み出しセンサーと強力なプロセッサを手に入れられるかどうかがパナソニックにとって鍵となるだろう。
DPReview
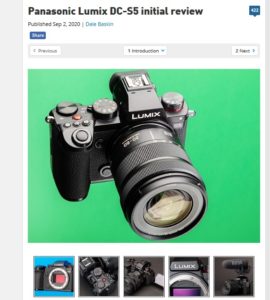
DPReview:Panasonic LUMIX DC-S5 initial review
目新しいポイント
- パナソニックのカメラは動画の代名詞となっているが、S5も例外ではない。フル画角モードでは最大4K 30pで利用でき、APS-C/Super35モードやセンサーのドットバイドット領域(1.56倍クロップ)を使用した場合は最大4K/60pの動画を4:2:2 10Bitカラーで撮影することができる。
- 熱管理のため、10Bitカラーで撮影する4Kモードと8Bit 4K 50/60pで撮影する4Kモードでは、30分間の記録制限が発生する。8Bit 4Kモードと10Bit FullHD記録を含むすべてのFullHDモードでは、無制限の記録時間が可能だ。
- S5は、S1Hと同様にログレコーディング機能を搭載し、波形モニタ、デュアルゼブラ、カスタムLUTのアップロード機能などを搭載している。
- また、デュアルネイティブISOを搭載しており、低いISO値では最大のダイナミックレンジを、高い値ではノイズ性能を向上させることができる。(訳注:手動切替はできません)
- アナモフィック特有の手ぶれ補正機能を備え、センサーの一部をトリミングしたアナモフィック撮影モードにも対応している。
- 可変フレームレート機能は、スローとクイックを意味する「S&Q」にリブランドされた。4K/60pと1080/180pまでのフレームレートを利用することができ、従来と根本的な違いはない。ただし、スロー端に1fpsのオプションが追加され(2fpsから更新)、最終出力ファイルに24pのオプションが追加されている。
- 動画業界のトレンドの変化に対応するため、カメラは垂直方向の録画に対応しており、自動的に向きを検出して動画を垂直形式で再生することができる。
- オートフォーカスは標準的なコントラスト検出AFと各レンズの光学特性を組み合わせて、空間認識AFシステム(DFD)で被写体までの距離を計算し、それに応じてレンズを駆動する。
一般的に像面位相差AFがより洗練されたものになっているが、パナソニックはこの技術の改良を続けている。 - S5のAFの改良点は、ディープラーニング技術による被写体認識の向上と高速化、DFDの計算方法の改善の2つに大別される。
- まず、S5では「顔、目、体」の認識に加えて、「頭部」の認識アルゴリズムを搭載しており、被写体がカメラから離れてもカメラが苦戦しにくいようになっている。
また、フレームに占める顔の割合は、他のSシリーズカメラの「5%」から、「2.5%」となった。
このほかにも、ボディと顔のオートフォーカス検出回数が、同社他機種でそれぞれ1秒間に12回、30回であるのに対し、S5では1秒間に60回計算できるようになっている。 - 第二に、S5は従来モデルよりC-AF中にDFD技術の依存度が高くなっている(コントラスト検出の依存度が低くなっている)。
これについての詳細は後ほどレビューするが、使用中にハンチングやリフォーカスの「フラッター」が少なくなっている。ハンチングやりフォーカスは気が散り、動く被写体を追いかけるのが難しくなる要素だ。 - このAF方式で最も課題が残されているのは動画撮影時だ。動画撮影時に静止画と同じような方法・レートでサンプリングすることが出来ない。
しかし、頭部検出機能のおかげで、優れた被写体追従性を発揮するはずだ。 - ライブビューコンポジットは目新しい機能では無いが、フルサイズモデルで導入するのは初めてだ。
- センサーを動かしつつ、8回の撮影でべイヤーフィルターの効果をキャンセルし、解像度を4倍に高める撮影モードを搭載している。LUMIX S1・S1RではRAW出力しか対応していなかったが、S5では直接JPEG出力にも対応している。
ハイレゾモードは被写体ブレ優先・解像度優先の2モードが用意されている。どちらのモードでも三脚が必要だ。 - 高解像度カメラでは、シャッター機構の振動により画像の手ぶれが発生することがある。一般的な解決策は、機械式シャッターの代わりに電子先幕シャッター(EFCS)を使用することだ。しかしEFCSには、非常に高速なシャッター速度でボケの外観に影響を与えるなど、独自の欠点がある。完璧を目指すのであれば、カメラは必要なときにはEFCSを使用し、そうでないときには機械式シャッターに戻す必要がある。
S5はまさにそれを目指しており、使用される特定のカメラとレンズの組み合わせに基づいてEFCSと機械式シャッターを自動的に切り替えることが可能だ。 - S5は、ミドルレンジのフルサイズカメラセグメントの真ん中に位置し、フルサイズ市場で最も競争の激しいカテゴリーである。主な競争相手は、同じような価格帯で発売されたソニーのα7 IIIやニコンZ 6であるが、一般的には発売から数年後の価格で販売されており、キヤノンEOS R6は他のグループよりもやや高価である。
- スペック的には、S5は同業他社の中では確かに競争力があると思う。高速連写が必要な時に選択するモデルでは無いが、大部分は競合他社と似ており、EOS R6と並び、グループの中では優れた動画性能を備えている。
- しかし、LUMIX S5はスペックシートでは明らかにされていない、動画撮影で役に立つ便利な機能をいくつか備えている。
ボディ・操作性
- S5の特筆すべき点は、そのボディの大きさだろう。これまでのパナソニックのフルサイズカメラは、ミラーレスの中で大きなの部類に入る。
- それに対してS5は、第4世代のソニーa7よりも一回り大きいが、重厚なS1よりもコンパクトな印象を受ける。
- このコンパクトサイズにトレードオフがないわけではない。熱管理のために、10Bit動画モードでの撮影時間の制限など、動画機能でいくつかの譲歩をしなければならない。
- 背面パネルはS1と同様、ダイヤル・AFモードセレクター・ボタンの配置はほぼ同じだ。ただし、「戻る」と「ゴミ箱」が一つになっている。これは最近のパナソニック機種を使ったことがある人なら、すぐに馴染めるだろう。
- S5のファインダーは236万ドットのOLEDパネルを採用しており、S1シリーズの576万ドットパネルや同クラスの他社製カメラで使われている369万ドットパネルよりも解像度が低い。アイポイントは20mm、倍率は0.74倍と、平均よりも一回り小さく長くなっている。
- ファインダーのリフレッシュレートは60fpsまたは120fpsに設定でき、表示ラグは0.005秒と非常に短い。これにより、非常に満足のいくユーザー体験を得ることが可能だ(高解像度では無いが)。
- S5では、S1の丸いアイカップではなく、より長方形のアイカップを採用している。底面にはアイセンサーが付いており、ユーザーがカメラを目の前に上げると自動的にピントを合わせ始めるアイセンサーAFを作動させることが可能だ。
- また、同じセンサーで「パワーセーブLVF撮影」という機能にも対応しており、ファインダーから目が離れたことを検知して自動的にスリープモードにしてくれる。逆に、ファインダーを目の前に上げると、直前の撮影モードが瞬時に復元される。パナソニックは、この機能を使えば、バッテリーでの撮影枚数を3倍にできると主張している。
- 動画撮影者に喜ばれる3.0型バリアングルモニタを搭載している。G100と同じ184万ドットのパネルを採用しており、屋外での撮影を想定した非常に明るいモニタだ。S5では色精度を重視して明るさを抑えているが、S5ユーザーはこれを理解すると思う。
- S5に3.5mmマイクとヘッドフォン両方のポートが搭載されているのは驚くことでは無い。マイクレベルまたはラインレベルの入力に対応し、必要なマイクにファンタム電源を供給することが可能だ。また、2つのXLR入力チャンネルと物理的なコントロールダイヤルを備えたパナソニックのマイクアダプター「DMW-XLR1」にも対応している。
- オーディオレベルは、-12dBから+6dBまで、最大18段階の調整が可能だが、S5にはS1Hに搭載されているハイ/ローゲイン機能は搭載されていない。
また、S1HやVariCamモデルに搭載されている、より高度な動画ステータス表示モードは搭載されていない。 - 動画出力は、Micro HDMIポートに対応している。動画撮影に多く使用されるカメラならフルサイズHDMI接続であって欲しいと思うが、GH5よりも小さなフルサイズミラーレスを手に入れるために支払うべき代償かもしれない。
- 新型バッテリーDMW-BLK22を使用している。GH5やG9のような大型Gシリーズカメラで使用されている「DMW-BLF19」バッテリーとサイズと形状が似ているものの、追加の電気接点が含まれており、約15%以上の容量を確保している。
新バッテリーは、より大きなGシリーズモデルと下位互換性があるものの、上位互換には対応していない。つまり古いBLF19バッテリーは、S5では動作しない。 - 新しいドロップイン充電器は、USB-C接続を介して充電する。GH5やG9のBLF19バッテリーを充電することが可能だ。しかし、古いGシリーズの充電器でS5の新しいバッテリーを充電することは出来ない。
- 撮影中にUSBから直接電源を供給することも可能で、インタビューやライブイベントの撮影時など、バッテリー交換が面倒なときに便利だ。
別売りオプションのバッテリーグリップ「DMW-BGS5」も用意されています。 - S5にはデュアルSDカードスロットが搭載されており、1つはUHS-IIカードに対応し、もう1つはUHS-Iカードまで対応している。
2つ目のカードスロットの速度は低速だが、どちらも最高ビットレートを処理するのに十分な速度であり、動画のパフォーマンスに影響は無い。
ただし最高連写速度でRAWファイルを出力し、スロット2にファイルを書き込む場合、U3カード30MB/sのレートがボトルネックになるため、静止画のパフォーマンスに影響がある。 - SDカードは録画中にホットスワップが可能だ。USB電源と8Bit録画であれば、実質的に無制限の録画時間があることを意味する。
- パナソニックはファームウェアアップデートを予告しており、2020年末までに実装が予定されている。 S1Hとのギャップをさらに縮める追加機能が含まれている。
・DCI 4K
・HDMI出力 RAW動画
ーAtomos Ninja V
ー16:9 5.9K 30p
ーSuper35モード 4K 60p
・ベクトルスコープ
・マスターペデスタル
・シャッター角
・dB表示
・LモノクロームS
・Lクラシックネオ
ファーストインプレッション
パナソニックが最初にフルサイズカメラ市場に参入したとき、文字通りの大型化した。S1とS1R(そして後のS1H)は、ミラーレスの基準としては大きなボディだった。確かに印象的なカメラであることは間違いないが、その大きさは万人の心の響くものでは無かったはずだ。
パナソニックは、ソニーα7 IIIやニコンZ 6のようなものに対抗する、コンパクトで2000ドル前後のフルサイズモデルを持っていなかったのである。
そこでS5の登場だ。S5はフルサイズ市場で競争力を持つために、パナソニックが作らなければならなかったカメラである。パナソニックがフルサイズ市場に参入する際、多くの人が期待していたカメラでもあると思う。静止画と動画の両方に優れたコンパクトなモデルであり、長時間動画撮影機能を備えたGH5に近いフルサイズミラーレスだ。GH5よりも少し小さくなったが、ほぼ実現している。
これまでのところ、S5について最も高く評価しているのは静止画と動画のバランスが優れていることだと思う。S1と同じセンサーを搭載した堅実なスチルカメラであり、写真家のためのクリエイティブなツールをいくつか搭載している。
夜空撮影にライブコンポジットモードを試すのを楽しみにしているし、多くの人が更新されたハイレゾモードを楽しむだろう。動画撮影をする予定がなくても、好きになるところがたくさんある。
もちろん動画撮影ができなければ、ハイエンドのパナソニックカメラではない。より高価なS1Hほどでは無いが、S5は良いバランスの機能を備えている。
実際に、S5のターゲット層のほとんどの人は、おそらく最高ビットレートのALL-Iコーデックを必要としていないだろう。それでも、撮影時に役立つ優れたアシスト機能を実装してくれたことは嬉しく感じるはずだ。
そして、パナソニックが機能と熱管理のバランスを取っていることを評価している。
S5で最も気になるのはパナソニック独自のDFD AFシステムかもしれない。パナソニックはDFDの改善を続けており、我々はまだ大規模なAFテストを行っていないが、C-AFを使用する場合に、いくらか改善を見ることができると思う。
S5の動画AFは最新カメラに搭載されている位相差AFに比べて、まだ洗練されていないように感じた。動画撮影ではマニュアルフォーカスを多用し、AFの重要性が低いとよく言われている。しかし、最新の位相差AFシステムは多くの場面で有用であることを証明している。
長い間、パナソニックのカメラを使って動画撮影をしてきたが、クラストップレベルの動画システムの中で、DFD AFがアキレス腱になっていることもあった。私はパナソニックのDFD改善を評価しており、十分な先進技術(より多くの処理能力とより高速なスキャンセンサー)があれば、本当の可能性があるように思える。
その一方で、競合他社はDFDの気が散るような挙動を示さない効果的な動画AFシステムを実装している。
間違いなくパナソニックがこれまでに生産したカメラの中で最も汎用性の高いカメラの一つだ。専門分野においてハイパフォーマンスを発揮するカメラでは無いが、何でも屋のような存在に慣れるカメラである。
クラスをリードするカメラにはなれないが、ほとんどの分野ではかなりの競争力があるはずだ。
Mobile01

Mobile01:【外觀實拍】Panasonic S5全幅中階機正式發表!雙原生ISO、2420萬畫素還有更小巧的機身
- パナソニックはまず最初に大型のLUMIX S1・S1Rを投入し、次はさらに大きなLUMIX S1Hを投入した。この路線で行くのかと一抹の不安を覚えたが、どうやらパナソニックは普通のミラーレスカメラのサイズを把握していたようだ。
- LUMIX S5は比較的コンパクトなミラーレスカメラであり、ポジション的にはミドルレンジだ。
- 基本的に見た目はS1であり、操作性も非常によく似ている。しかし、送られてきた試用品の箱のサイズで一目瞭然だ。
- ハンドリングでは明らかな違いがある。S1はモンスタークラスのボリュームで、背が高く深く厚いグリップを備えている。ボディサイズはデジタル一眼レフ並みだ。
その一方、このS5はS1より一回りボディサイズが小さい。ソニーα7シリーズより僅かに大きいが、キヤノンEOS R5・R6ほどでは無い。そしてS1の良好なグリップは維持されている。 - 重量は714gであり、S1の1021gより遥かに軽量だ。
- 2420万画素センサーを搭載し、6.5段分のDual.IS・5.0段分のボディ内手ぶれ補正に対応している。
- 動画機能
4K 60p 4:2:0 10Bit 内部記録
4K 30p 4:2:2 10Bit 内部記録
14stop以上のV-log・V-Gamut
アナモルフィック
5.9K 30p RAW・Cinema 4Kにファームウェアで対応 - 常用ISO感度は100-51200だ。拡張感度でISO50とISO204800を利用可能である。
- S1HとGH5Sにのみ実装しているデュアルネイティブISOに対応している。(訳注:回路の手動切替は出来ません)
- RECボタンの位置はGH5SやS1Hを継承している。
- HDMIポートはパナソニックでは珍しいMicro HDMIに対応している。このことからLUMIX S5の位置付けを窺い知ることが出来る。
- メモリーカードスロットは上部スロット1がUHS-II対応、下部2スロット2はUSH-Iのみ対応している。
- グリップ側面にはリモートレリーズ端子用のポートがある。
- 電子ファインダーは236万ドットだ。S1シリーズの576万ドットと比べると低解像だが、どちらも120fpsで駆動する。
- 小さなAFジョイスティックを搭載している。しかし、使ってみたところ、S1シリーズと比べて少し浅く、操作感が明瞭ではないと感じた。
- ボディサイズをS1と比べてみると、違いが分かる。全高はちょうどS1の「LUMIX」ロゴくらいである。
- ステータスLCDの代わりにモードダイヤルを搭載している。S1シリーズは左肩の同軸上にモードダイヤルとドライブダイヤルが存在する。
- 基本的に背面ボタンは配置を除けばS1Rとほぼ同じだ。S1シリーズを使ったことがあれば使いやすいはずだ。そしてボタン位置も大きな差は無い。
- S5は一般的なバリアングルモニタだが、S1・S1Rは3Wayタイプのチルトモニタだ。S1Hはチルトとバリアングルモニタが完全に融合している。
DPReview

DPReview:Hands-on with the Panasonic LUMIX S5
- パナソニックLUMIX DC-S5は、同社のLマウントミラーレスカメラのフルサイズシリーズで、より安価な新モデルである。既存のモデルよりも小型・軽量で、静止画撮影と動画撮影の両方に対応している。
- S1と同じ24MP BSI CMOSセンサーをベースにしているが、その他の仕様は多くの点で異なっている。
- パナソニックは、既存のカメラ(少なくともファームウェアのアップデートが他のモデルに適用されるまで)よりもいくつかオートフォーカスの改善点について言及している。
- 同社は、このカメラを高く評価するユーザーとして、「ハイアマチュア」と「映像クリエイター」を挙げている。
- S5は、S1、S1R、S1Hよりも明らかに小さい。実際、同社のマイクロフォーサーズシステムの動画主力モデルであるLUMIX DC-GH5よりも僅かに小さい。そしてS1よりも約30%軽い。
- この小型化は、いくつかの設計変更によって可能となっている。小型バッテリーの採用、カメラ上部の液晶設定パネルがなくなったことが最も大きな変更点だ。
- ボディは相変わらずマグネシウム合金製で、大掛かりな耐候シールが施されているのが特徴である(パナソニックは大型モデルと同等の凍結耐性は主張していない)。
- S5では、シンプル化された部分として、カメラの表示パネルのスペックがある。S5は236万ドットのOLED電子ファインダーと、3.0型184万ドットの背面液晶ディスプレイを採用している。動画・静止画撮影に重点を置いているため、S1のように静止画撮影に適した3Wayチルトではなく、バリアングル式となっている。
- S5は、S1やS1Hと同じ24MPセンサーを採用しており、ローパスフィルターは搭載していない。
- 「自動デュアルネイティブISO」と説明しているデュアルゲインチップだが、これはS1、Nikon Z6、Sony α7 IIIと同様、高ISO感度モードでより高いゲインの読み出しモード(読み出しノイズが少ない)に切り替わることを意味している。S1Hとは異なり、切り替えポイント付近のISOで、どのゲインモードを使用するかを選択することはできない。
- S5は、S1と同様に5段補正の5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載しており、レンズ内手ブレ補正機構との連携により、「Dual.IS 2」対応レンズで6.5EVの補正を実現している。
- CAFで最大5コマ秒、SAFで7コマ秒の撮影が可能だ。
- 三脚に装着した場合、S5は手ぶれ補正システムを使用して、9600万画素のハイレゾ撮影が可能だ。S1と異なり、RAWファイル出力限定ではなく、JPEGを直接出力することが可能だ。
- ハイレゾモードはこれまでのパナソニックのカメラと同様、最大解像度を優先するモードと、撮影の合間に起こったブレを補正するモードがある。最新システムでは、1フレームあたり最大1秒だったシャッタースピードが8秒まで使用可能となっている。
- S5にはSDカードスロットが2つあり、1つはUHS-II、もう1つはより遅いUHS-Iタイプを採用している。
- マイクとヘッドフォンの両方の端子に対応している。マイク入力は、一般的なマイクレベルまたはラインレベルの入力に対応しており、必要に応じて外部マイクに電源を供給することも可能だ。
- 他のSシリーズカメラのようなフルサイズのHDMI A端子ではなく、「マイクロ」HDMI D端子に対応している。
- デュアルバンドWi-Fiも搭載されており、Wi-Fiネットワークへの5GHz接続やスマートフォンへの2.4GHz接続をより高速に行うことが可能だ。
- S5は安価なモデルであるにもかかわらず、印象的な動画仕様である。S1と同様、Super35(APS-C)クロップまたはドットバイドット(やや大きい1.56倍クロップ)で、4K UHD 30pまたは4K UHD 60pで撮影可能だ。
- 最も注目すべき点は、V-Log機能が含まれていることだ。30pまでのモードでは4:2:2、60pでは4:2:0 10Bitの撮影に対応している。また、HDRディスプレイに最適化されたハイブリッドログガンマ映像の撮影も可能だ。利用可能なコーデックとビットレートは、有償アップグレードをインストールしたLUMIX S1と基本的に同じだ。
- 50pまたは60pでの4K撮影時、または10ビットの4K映像を撮影した場合、最大30分間の撮影が可能だ。30p以下での撮影には制限はない。パナソニックによると、これは40℃環境でのテストに基づいており、極端な環境温度では最終的にカメラが録画を停止する可能性があるという。
- 大きな特徴としては、オートフォーカスが向上したことが挙げられる。最も大きな変化は、静止画の連写撮影時だ。パナソニックによると、被写体認識アルゴリズムを再構築し、AFシステムがより多くの空間認識計算を行えるようにする方法を開発したそうだ。これにより、連写時のハンチング(ファインダーのバタつき)が軽減されるという。
- 動画のオートフォーカスでは、カメラが正しい被写体にピントを合わせるという点で、頭部認識が追加され、認識アルゴリズムが高速化されたこともメリットとなっている。応答性と安定性の改善もあるが、その多くは主に読み出し速度が速いSuper35の映像に適用される。
- 改良されたフォーカスの安定性の一部は、フルサイズの24p動画(これはカメラの最も遅い読み出しモードを使用している)にも適用されるはずだが、必ずしも応答性が向上しているわけではない。
- S5はDMW-BLK22と呼ばれる新しいバッテリーを使用している。GH5に使われているものとサイズは似ているが、形状が少し違うので、古いバッテリーはS5では使えない(新しいバッテリーは古いカメラでも使えるが)。
- 新しい外部充電器は、新旧両方のバッテリーを充電することができるが、新しいBLK22バッテリーは、古いカメラに付属する充電器には対応していない。
- 15.8Whのバッテリーを搭載し、背面液晶を使用した場合は1回の充電で440枚、ファインダーを使用した場合は1回の充電で470枚の撮影が可能だ。
- USB Type-Cを介して、USB-PD対応の充電器やモバイルバッテリーを使用して充電または給電することができる。
全体的に、LUMIX S5はパナソニックSシリーズの興味深い新モデルだ。発売価格は、Nikon Z6やSony α7 IIIのようなカメラと競合する。しかしこれらは、発売から18ヶ月以上が経過し、希望小売価格から下がっていることを考えると、これらのカメラ(そしてより良いスペックのS1でさえも)と比べると、最初は高価に見えるのは必然である。
他のモデルも2020年末までにS5で改善されたオートフォーカスの恩恵を受けると言われている。現時点では優秀な静止画/動画のハイブリッドミラーレスと言えるだろう。そして、パナソニックは後日、LUMIX S5にDCI 4K, RAW動画出力とシャッター角コントロール(訳注:シャッタースピード調整方法の一つ)を追加する無料のアップデートを公開すると言及している。
速報履歴
噂情報のまとめ

- 純正アクセサリーに「S5」と掲載された時期があった
- 海外販売店で「S5 ボディ」「S5 20-60mmレンズキット」発売の動きあり
- スペックシート
- 税込量販店価格:ボディ 275,000円・20-60mmキット 319 ,000円
2020-09-01:国内での価格設定
パナソニック「LUMIX DC-S5」の税込量販店価格はボディ275,000円、20-60mmキット319 ,000円になるらしい。#噂https://t.co/hw4Nk69XMY
? 軒下デジカメ情報局 (@nokishita_c) September 1, 2020
2020-08-16:スペックシート
パナソニック「LUMIX DC-S5」のスペックシートが海外のニュースサイトに掲載されました。#噂https://t.co/5rIb8Ggs0T
? 軒下デジカメ情報局 (@nokishita_c) August 14, 2020
ココがポイント
- フルサイズ 2420万画素 CMOSセンサー
・5軸 5段 ボディ内手ぶれ補正
・センサーシフト式除塵ユニット
・HLG Photo対応 - デュアルSDカードスロット
Slot1:UHS-II対応
Slot2:UHS-I対応 - ISO感度 50-204800
・常用ISO感度 100-51200?
・デュアルネイティブISO
-スタンダード
-V-Log
-HLG
-Cinelike - コントラスト検出AF
・225点
・測距輝度範囲:EV-6~20
・人体、動物検出(225点・ゾーン) - メカニカルシャッター:1/8000?60秒
電子先幕シャッター:1/2000-60秒
電子シャッター:1/8000?60秒
フラッシュ同調速度:?1/250秒 - AFS連写速度:?7コマ/秒
AFC連写速度:?5コマ/秒 - 連続撮影枚数:RAW 24枚
- OLED 236万ドット 0.74倍ファインダー
- 3.0型 フリーアングル 184万ドット 液晶モニタ
- 4K 60p 4:2:2 10Bit LGOP 150Mbps
- FullHD 60p 4:2:2 10Bit LGOP 100Mbps
- アナモルフィック4K対応
- ハイフレームレート 4K 60fps・FullHD 180fps
- 4K 60p時はAPS-C・ドットバイドット
- 波形モニタ・V-Log 初期装備?
- USB 3.1 Gen1 C端子
- HDMI D端子
- 3.5mm マイク・ヘッドホン端子
- 5GHz WiFi・Bluetooth
- サイズ:132.6×97.1×81.9mm
- 重量
・SDとバッテリー含む:714g
・ボディのみ:630g
LUMIX S1より低価格なエントリーモデルという噂もありましたが、動画機能はLUMIX S1の初期装備より優れています。ソフトウェアキーの購入で対応するV-Logや波形モニタを実装し、S1Hしか対応していないアナモルフィック4Kも利用可能と言うのは凄いですね。
ただし、ボディサイズは従来のLUMIX Sシリーズよりも小さく軽量。連写速度は抑えられ、センサー除塵ユニットは簡略化されています。
個人的に気になるのはAFエリア「ゾーン」で人体検出や動物検出が使えそうなスペックシートの表記となっていること。従来モデルは225点オートエリアのみ対応しており、任意のフォーカスエリアを指定することが出来ません。このため、複数の被写体が存在したり、誤検出した場合のリカバリが難しいのですよね。これがゾーンAFエリア内の検出に対応するとさらに使いやすいAFシステムとなるような気がします。今のところそのような動作に対応しているのはソニーαシリーズのみのはず。
2020-08-14:LUMIX S5が近日中に登場濃厚か?
パナソニックのフルサイズミラーレスカメラ「LUMIX S5 Body」と「LUMIX S5 20-60mmレンズキット」が海外の販売店に先程登録されました。#噂
? 軒下デジカメ情報局 (@nokishita_c) August 14, 2020
以前にパナソニック純正アクセサリ対応表でフライング掲載されていた「S5」が近日中に登場しそうな気配となってきましたね。詳細は全く不明ですが、キットレンズが「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6」であることから、比較的エントリー寄りの機種となるのではないかと思われます。
LUMIX S1やS1Rと比べて、性能差・価格差が気になるところですねえ。
サイト案内情報
LUMIX Sシリーズ関連記事
- ツアイス Otus ML1.4/35 のリーク画像
- XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR レンズレビューVol.4 諸収差編
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD E/Zマウント のスペックとリーク画像
- 旅行用レンズを最小限に抑える魅力的な選択肢|XF23mmF2.8 R WR
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXDのリーク画像
- RICOH GR IV Monochrome レビュー
- キヤノン EOS R10 Mark II は2026年後半に登場する?
- XC13-33mmF3.5-6.3 OIS レンズレビューVol.3 遠景解像編
- コシナ SEPTON 40mm F2 Aspherical 最新情報まとめ
- RICOH GR IV 最新ファームウェアVer1.11配信開始|1/16000秒電子シャッター対応
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。